
- 登山者検診:登山者を対象とした人間ドック
- 登山者外来:心臓病を抱えている方が安全に登山を楽しめるようサポートするセカンドオピニオン外来
✓登山中に心臓病を発症してしまった・・・
✓心臓の手術を受けたけど山がやめられなくて、自己判断で登山を続けている・・・
なんていう方は実は少なくないのです。
2021年には八ヶ岳にある赤岳鉱泉に併設する赤岳鉱泉山岳診療所を開設し、現在も運営しています。
もちろん僕一人では無理なので有志の山岳医・山岳看護師とともに運営しています。










赤岳鉱泉は通年営業している山小屋で冬季にもたくさんの登山者が訪れます。
そんな赤岳鉱泉に併設された赤岳鉱泉山岳診療所は日本国内では唯一冬季も開設している山岳診療所です。
凍傷をはじめとした冬季特有の傷病を抱えた方もやってきます。
2024年にはフジテレビ系列で放送された 「マウンテンドクター」 の医療監修も務めました。
実は山岳医療・山岳医の立場はまだまだ低いというのが僕の認識です。
「山岳医療」というキーワードを少しでも多くの方に届けたくてドラマの医療監修を引き受けましたが、なにせ初めてのことだらけだったので想像以上に大変でした・・・汗)
安全登山に貢献するために登山医学に関する知識をより多くの方に届けたいという思いから、これまでも 登山者検診Facebook で情報発信をしてきました。
しかし、SNSでは過去の記事を探しにくく、情報が断片的になりがちです。そこで、「いつでも見返せる」「体系的に学べる」 場所として、このブログを開設することにしました。
本ブログでは、登山者の皆さんが安全に登山を楽しむための医学的な知識や、実践的なアドバイスを発信していきます。
なぜ「登山×医療」の情報が必要なのか?
登山は老若男女を満足させられる素晴らしいアクティビティですが、「医療リスク」「環境リスク」 という側面も持っています。
実際に山でこんな疑問を持ったことはありませんか?
- 高山病の予防や対策は?
- 登山中の熱中症を防ぐには?
- 持病(高血圧・糖尿病・心疾患)があっても登れる?
- 低体温症や脱水になったらどうする?
- 登山中にけがをしたときの応急処置は?
- 長期間の登山では、どんな健康管理が必要?
山の中というのは、医療機関からは隔絶された文字通り“野外(Wilderness)環境下”です。
山中で怪我をしても、病気を発症しても、すぐに救急車は来ません。
携帯電話が繋がるとは限りません。
たまたま携帯が繋がって、救助を呼べても、山岳救助隊が到着するまでに最低でも数時間はかかります。
つまり、
自分や仲間を守れるのは「自分自身の登山医学の知識」になります。
僕自身、山岳医として登山者検診/登山者外来を実施する中で登山者の体力レベルや健康状態を目の当たりにしたり、山岳診療所で登山中のトラブルに対応する中で、登山者自身が山岳医療・登山医学の知識を持つことの重要性を強く感じています。
このブログでは 「登山者が知っておくべき医学的知識」 をわかりやすく解説し、皆さんの 「安全な登山」 に貢献できるような情報をお届けします。
さらに「山岳医療を志す医療従事者にとっても有益な情報」を発信できるよう頑張りたいと思います。
本ブログの主なテーマ
このブログでは、以下のような内容を発信していきます。
山岳環境リスクへの対策
- 高山病のメカニズムと予防法
- 高所順応の方法
- 高山病になったらどうする?
- 低体温症とは?どのように判断するのか?
- 凍傷の特徴とファーストエイド
- 熱中症・脱水の予防と対策
- 雷撃症に出会ったら・・・
体調管理
- 登山中の水分管理
- 登山中のカロリー管理・栄養管理
- 登山時の心拍数・血圧管理(特に持病がある方へ)
- 登山に向けたトレーニング・ケア
- 膝痛対策
- 筋肉痛対策
- こむら返り対策
- 登山者検診・登山者外来とは?
登山中のファーストエイド
- 捻挫・骨折・擦り傷など創傷処置の考え方
- 頸椎保護の考え方
- 頭部外傷
- 体調不良時のファーストエイド
- 応急処置に役立つ登山用ファーストエイドキットの選び方
- 遭難対策・リスクマネジメント
持病と登山
- 登山と心臓突然死の関係
- 高血圧の人が抱える登山のリスクは?
- 心疾患・ペースメーカーがある人の登山の注意点
- 糖尿病登山者の血糖管理とエネルギー補給
装備レビュー
- 山岳医視点での装備・ギアの選び方
山岳医療・登山医学に関する論文の紹介
これらの情報をできる限り医学的なエビデンス に基づきながら、登山者目線で実践的に役立つ形で発信していきます。
注意点
山岳医療・登山医学の分野では、街中の医療と異なり医学的エビデンスが乏しいといったことが多々あります。
医療資源の限られた山中においては街中の医学的エビデンスをそのまま転用できないという場合もあります。
そのあたりはできるだけ気をつけながら自分なりの意見も踏まえて発信していきます。
このブログを閲覧してくれる医療従事者の方はそのあたりを理解して、「ブログに書いてあったから・・・」という理由だけで実際に医療行為を行わないように注意して下さい。
プロの皆さんはきちんと自ら情報源を当たって自らの責任で適切な行動をよろしくお願いします。
登山者が登山医学を学ぶことのメリット
「医療の知識がなくても登山はできる」と思うかもしれません。
しかし、登山医学を少し知るだけで、より安全に、より快適に登山を楽しむことができます。
✅ 山でのトラブルを未然に防げる
→ 例えば、「脱水症になりやすい状況」を知っていれば、事前に水分補給を工夫することができます。
皆さんは脱水症の具体的な症状がわかりますか?
自分が脱水なのかどうか判断出来ますか?
✅ もしもの時の対応ができる
→ 仲間が低体温症になったとき、適切な対応ができれば、重症化を防ぐことができます。
✅ 自分の体調をより深く理解できる
→実は隠れ心臓病を患った状態で登山をしている方は少なくありません。
→逆に 「持病があるから登山を諦める」ではなく、”正しく知ることで無理のない登山が可能に”なります。
まとめ 〜「安全で楽しい登山」をサポートするブログへ〜
このブログでは、「登山×医療」の視点から、安全で快適な登山をサポートする情報 を発信していきます。
僕自身、山岳医療・登山医学を学びながら登山を続けている立場として、「医学的なエビデンス」と「実際の登山経験」の両方を活かした実践的な情報を提供 したいと思っています。
また、登山者の皆さんの疑問や相談にも応えていきたい ので、ぜひコメントやお問い合わせを通じて、気になることがあればご質問ください。
このブログが、登山を愛する皆さんにとって 「役立つ情報源」「困ったときの参考書」 となるよう、これから記事を更新していきます。どうぞよろしくお願いします!
「こんな情報を知りたい!」ということがあれば、是非コメントを下さい。
参考にさせていただきます!
書籍紹介
以下に僕が監修した書籍をご紹介します。
興味がある方は是非読んでみてください。
👇こちらは大人気の笹倉ガイドの本です。ファーストエイド部分を執筆・監修させていただきました。
Kindle unlimitedは月額980円で読み放題です。
・山岳ドクターがアドバイス 山のダメージ&体のトラブル解決法
・完全図解 山岳セルフレスキュー教本
この2冊はKindle unlimitedで両方とも読めてしまうので、Kindle unlimitedもオススメです。
\ 月額980円で読み放題 /


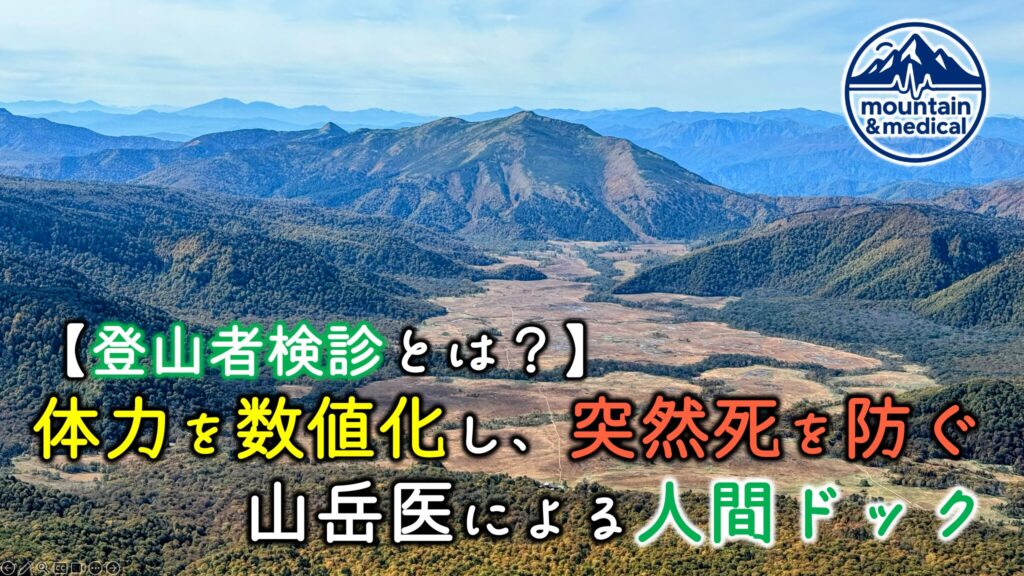
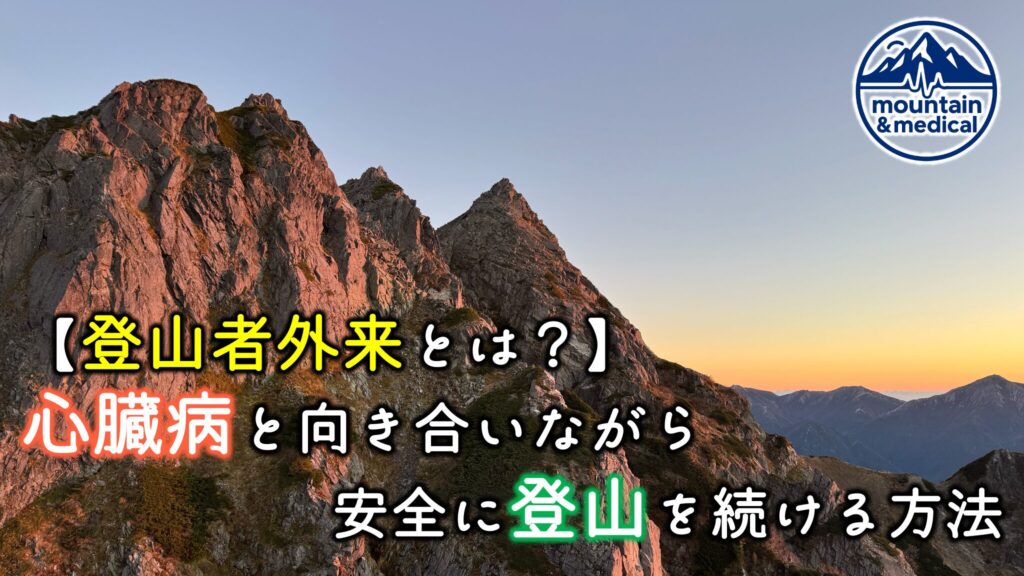



コメント
コメント一覧 (6件)
市川先生
大阪の遠藤です。
まだブログの全てを読破した訳ではありませんが、身体の機能や仕組みに元々興味があり、尚且つ登山を趣味とする者としては身体の仕組みや機能、疾患等が登山と言う特殊な環境下ではどのような影響を受けどう身体に変化を及ぼすのか?に常々興味を持っていました。
また私自身が軽度ながら慢性腎臓病と診断されたり、頻拍の不整脈持ちと言う事から
気になった時に気になった事をピンポイントでネットで検索し調べてみたりしていましたので、登山と医療に関しての情報を体系的に学べる何かをずっと探していました。ですので市川先生の今回のブログ開設は正に私が待ち望んでいた世界です!
先生が書いてらっしゃるように登山×医療の参考書が欲しかったので、お忙しい中のブログ更新は中々大変かとお察ししますが今後ブログを楽しみにしています。そしていつか本当に参考書となる書籍の出版などもご検討頂けると更に嬉しく思います。
長々と失礼しました。
遠藤さん
ご無沙汰しております。遠藤さんの期待に応えられるように頑張りますので、多くの人に読んでもらえるようにお知り合いにも伝えて下さい!
また、「こんなことが知りたい」なども適宜教えて下さい。参考にさせていただきます。
お世話になります。
早速以下3項目について質問させて頂きます。
かなり長文になるかと思います。
①高山病予防薬ダイモックスについて
②山小屋での睡眠導入剤について
③持病(慢性腎臓病)と登山の運動強度について
①以前も少しだけ先生に伺った事がありましたが、高山病予防薬のダイアモックスについて。
私は多分ですが高所に弱いかと思います。その時の体調やコンディションによりますが、標高2500mぐらいでも軽い高山病の症状、頭痛や生あくび、倦怠感等が出る時があるので、対策としては本番の3000m峰に行く1ヶ月ぐらい前に2500~3000mぐらいの山に行くようにしつつやはり心配なのでダイモックスを山行前日から半錠ずつ予防として服用しているのですが、服用しない方が良いとの情報も目にしたりするので、何が正解なのか?何故服用しない方が良いのか?の疑問
②山小屋での睡眠導入剤について。
高所山小屋での睡眠導入剤は
睡眠中の呼吸が更に浅くなり酸素摂取量が減少するため、睡眠中から高山病が発症しやすくなる事からあまり推奨されないようですが、これも個人差があり私は服用せずに睡眠不足になる事で高山病や熱中症、はたまた私の場合は頻拍が起こったら…の不安から服用してでも睡眠を確保したいと考えてしまいます。幸い今まで導入剤を服用し翌日高山病的な症状を経験した事がないので、つい導入剤に頼ってしまいますが、医学的にはやはり推奨されないものでしょうか?
③腎臓病と登山の運動強度について。
これこそ個人差があり腎機能の程度による所だと思われ、市川先生の専門外だとは思いますが、一般的には疲労度の高く筋肉を酷使しするような登山、特にアルパイン系は腎臓に負担がかかる事から避けた方が良いとは思うのですが、運動強度に対する耐性にも個人差があるだろうと思い何を基準にするのが良いのか?判断基準に悩みながらの毎年の夏山です。(eGFR46~53の間を行ったり来たりで主治医からは運動に関してそれほど制限はされていませんが、正直登山の運動強度は分からないんだと思われます)
対策としては日頃からの体調管理(塩分6g以下)
月に2~3回の日帰り登山プラス週1回ジムでのランニング
定期的な検査にての経過観察
登山に関しては無理なスケジュールではなく、山小屋泊などを利用しつつ体力回復を計りながらの山行。
とにかく水分補給を意識
市販のタンパク尿検査薬紙マイウリエースTを持参しタンパク尿の状況確認。
暑い夏場のアルプスは避ける。
腎疾患だと夏場の山での適切な塩分摂取量も悩ましい所です。
以上が日頃疑問に感じている事です。特に③は個人的な持病に関する事ですし非常に判断基準が難しく個人の体力や体質、腎機能の個人差によるところだと思われますので、割愛して頂いても構いません。もし医学的に何かしら情報がありましたら取り上げて頂けると嬉しく思います。
かなりの長文失礼いたしました。
遠藤さん
返信が遅くなりすみません。ブログ運用になれておらず・・・。
コメントが書かれても特に通知が来なかったので、通知が来るような設定に変えられるのかまた調べてみます。
①高山病予防薬ダイモックスについて
ダイアモックスの効果はかなり個人差があります。
「すごく効果がある」という人もいれば、「全く効果がない」という人もいます。
そもそも高所へは順応すべきであり、遠藤さんがされているように、事前に山登りをしていく、あるいは初日は2500m以上へは上がらないようにするといった対策がまず重要です。
そういう意味で、「本来すべき高所対策をせずに薬に頼るのはよくない」とされています。
薬ですから当然副作用もありますからね。
そこで一般的には急激に高度を上げなければならない人(具体的には救助隊など)に関しては予防投与が推奨されますが、それ以外のケースでは推奨はされません。
僕も外来で希望されることがありますが、「薬だけに頼らないように指導した上で、希望者には出す」という感じです。
②山小屋での睡眠導入剤について
睡眠薬を飲むと睡眠が深くなるので必然的に呼吸は浅くなる傾向にあります。
したがって、教科書的には高山病リスクが上がるので推奨されません。
しかし、何事も個人差はあります。そもそも、睡眠時無呼吸がない方であれば睡眠薬を飲んだところで影響はほとんどないでしょう。一方で、もともと睡眠時無呼吸症候群といわれている方であれば如実に影響が出ると思います。
また、もともと高所に強いかどうかも当然影響します。
③腎臓病と登山の運動強度について
高度腎障害がある方が高強度の運動をすることはおすすめできません。
というか、高強度の運動は健康に良くないので誰でもおすすめできません(汗)
アスリートは基本的に不健康だと思ってください。短命の方が多いですよね。
健康的な運動とアスリートのような運動はそもそも目的が違いますので。
おっしゃるように高強度かどうかというのは絶対値があるわけではなく、相対的なものです。
アルパインであっても自身にとって高強度にならないように日頃からトレーニングを積むのがいいと思います。
ちなみに筋肉量が多い方は見かけ上、腎機能が悪い(クレアチニンが高い≒eGFRが低い)と言われやすいです。おそらくは遠藤さんのさほど腎機能は悪くないと思います。
主治医の先生がおっしゃるようにそこまで気にせず、今やってらっしゃる対策でいいかと思います。
登山中の飲水量や塩分摂取量についてはいつかブログで書きますので、お待ちください。
色々と勉強になる情報をありがとうございます。
幼少期に喘息があり、今は完治していて8,000m峰にチャレンジしています。
大人になってから不整脈がたまに感じられ、何度か心臓専門の病院に行き検査をしてもらったりしましたが、問診の際に登山経歴を伝えるとその瞬間から医師の顔色が変わり「問題ないでしょう」という言葉が毎回帰ってきます。普段は問題ないのでこれ以上はする事もありません。と言われて終わります。しかし不整脈が打つ鼓動?が年々強くなってきているのを感じます。
また心拍数も年々弱まり、安静時には50〜48位だったのが、最近では42〜44位が普通になってきました。不整脈きっかけや発生するタイミングも一過性がないので医師に説明もできず、そのまま年月が経っています。
自分の身体が今どうなっていて、何に気をつけて行けばよいのか、知るにはどうしたら良いでしょう。
岩田京子さん
コメントありがとうございます。
一概に不整脈といってもいろんな種類がありますし、ご年齢や登山歴、普段の運動習慣、既往歴などがわからないので、画一的にコメントするのが難しいですね。
8000m峰にチャレンジされるぐらいだからかなり努力されているのだとは思います。
一般的に受診される方が「不整脈」と表現していても実際には「不整脈ではない」ことも多々あります。
1つの方法としてはApple watchやGarminなど心電図を記録できるスマートウォッチを購入していただき、「不整脈」と感じるときに心電図を記録してもらい、医師に見てもらうのが一番手っ取り早いと思います。
治療が必要な不整脈なのか、治療が必要ない不整脈なのか、あるいは不整脈ではないのか。動悸症状を感じている最中の心電図をみれば一発で診断できます。
https://tozan-medical.com/arhythmia/#toc11
是非、上記記事のリンクから岩田さんにあったスマートウォッチを選んで購入をご検討ください。
当院の登山者検診、登山者外来を受けていただければもう少し具体的なアドバイスもできると思います。
現在、かなり予約が混み合っていますが、こちらも合わせてご検討ください。
受診時にスマートウォッチの心電図記録を持参してもらえるのがベストですね。